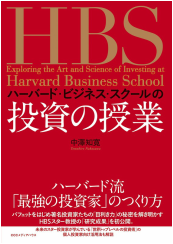|
予習の後は、いよいよ授業。80分の真剣勝負です。 授業のフローは、教授によって変わりますが、概ね以下の通りになります。 (1)コールドコール まず、「◯◯(ケースの主人公)が直面している問題は何か」、「貴方が◯◯なら、次はどうするか」など、ケースの土台となる事実や選択肢について、教授が質問します。最初の質問は、教授が学生一人を指名します。挙手ではなく、このように一方的に指名する質問の仕方は「コールドコール」と呼ばれています。確率的には、90人生徒がいるので1/90ですが、これがあるので学生たちは毎回ちゃんとケースを読んでくる、とも言われています。 (2)学生たちによる議論 コールドコールでは、更問も含めて10分ぐらい喋らされる授業もありますが、大抵の教授は2〜5分程度で他の学生たちにも参加するよう促します(なお、議論に参加することを学内用語で「get in」と言います)。 時間の制約から90人全員が発言することはなく、授業毎に約30~40名が目安。発言の機会が与えられることを学内用語で「air time」と言いますが、何せ成績の半分が発言の質と量(もちろん、質>量)にかかっていますので、air timeはまさに争奪戦となります。公平性を期すため、挙手して当てられるのは原則授業毎に一人一回となり、air timeはだいたい一人30~60秒が目安です。また、まずは当てられなければ始まらないということで、「効果的な手の上げ方」といったことまで、学校側はレクチャーをします(腕を真っ直ぐ、前のめりに、タイミングよく上げて、教授の目を見る、など)。冗談みたいな話ですが、そこまで皆が真剣だということです。 なお、ケースの対象企業 / 業界 / 国で働いていたなど、そのケースについて特殊な知識や経験を持つ学生がクラス内にいる場合は、その限りではなく、教授も積極的にその学生を当てにいきます。例えば、日本企業のケースでは、クラスで唯一の日本人だった私は何度も当てられ、発言の時間も長く与えられました。 授業中のディベートは奨励されています(「agree to disagree」と表現されます)。例えば、「X社によるY社の買収」がテーマとなっているときに、
といった具合です。なお、クラスメートに直接反論された場合は、それに対して反論する機会が与えられます。 もちろん、クラスメートの発言に賛同することもできます。クラスメートの意見に対して、新たな視点を提示して、サポートすることもできます。 授業中、教授は黒板に発言のポイントを次々と列挙していきます。その黒板に整理されていく内容を基に、どんどん議論を進めていき、そのケースで学ぶべきテイクアウェイへとクラスを導いていきます。これを、如何に自然に、そしてスムーズにできるかが、学生による教授の評価を左右します。 (3)テイクアウェイの整理とまとめ ケースの主人公(或いは、ケースの対象企業の関係者等)が実際にクラスに来訪することも多々あります。その場合は、授業終了20分前には議論は終わり、主人公から生の話を聞く、といった流れになります。 ケースの主人公が来訪しない場合は、最後の5分ぐらいでまとめに入り、ケースのテイクアウェイを整理します。また、ケースの主人公の最終的な判断やその後の展開を取り上げることもあります。 授業を振り返ってみて、テイクアウェイへとクラスが到達するうえで、特に有益だった発言に対しては、教授から高い評価が与えられます。学内用語で、「advancing the learning of other classmates(クラスメートの学びに資する)」と表現されています。 教授が個々の発言の質について授業中にコメントをすることはありませんが、良い発言をしたときには、授業後にクラスメートからポジティブなフィードバックを貰うことがあります。議論と言うと、どうしても敵対的や競争的なニュアンスがありますが、必ずしもそうではありません。授業中はお互いにベストを尽くし、終わったらその成果をフィードバックを通じて称え合い、認め合う。そういったことが自然にできるプロフェッショナルたちが揃っているのがHBSです。もちろん、学校側もそういったことを奨励しています。スポーツにおいても、「良い試合」はプレーヤーの能力はもちろんのこと、お互いのスポーツマンシップが体現されて初めて生まれますが、それに似ているのかもしれません。 Comments are closed.
|
Author投資プロフェッショナル。著者。投資、MBA、書籍などについて綴ります。 Archive
May 2017
Category |

 RSS Feed
RSS Feed